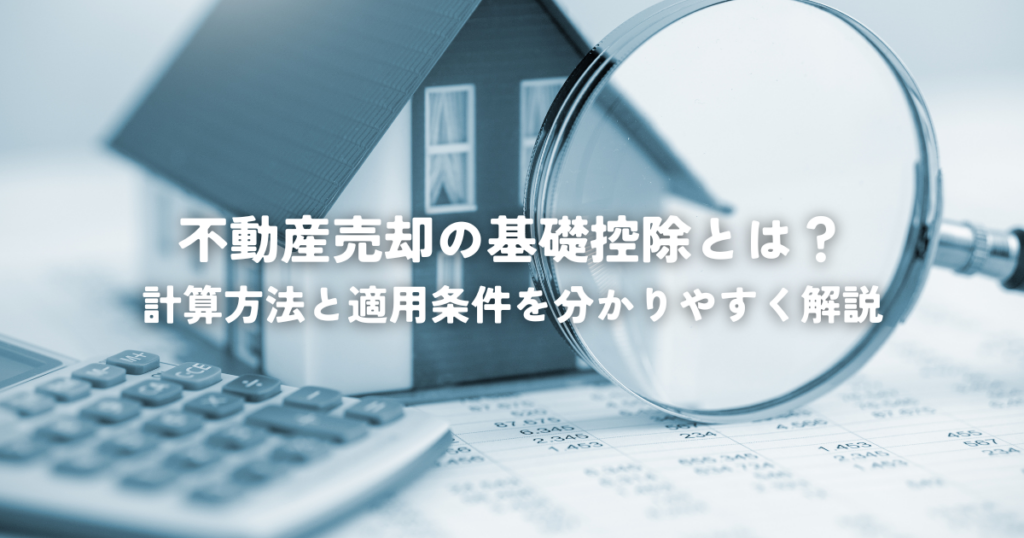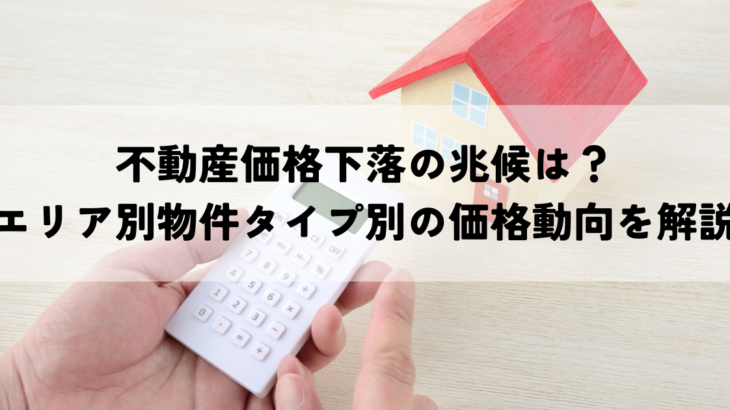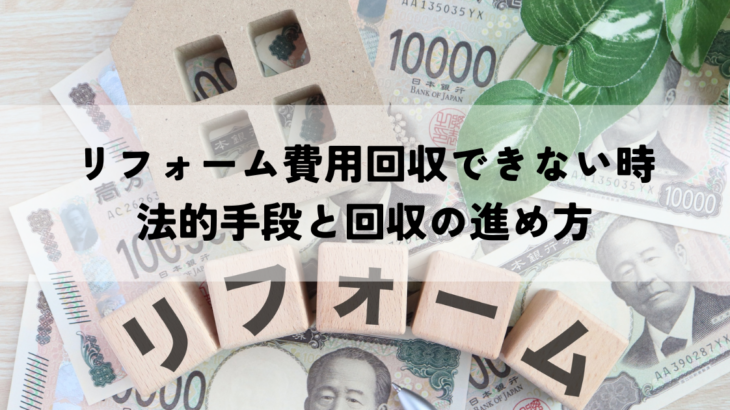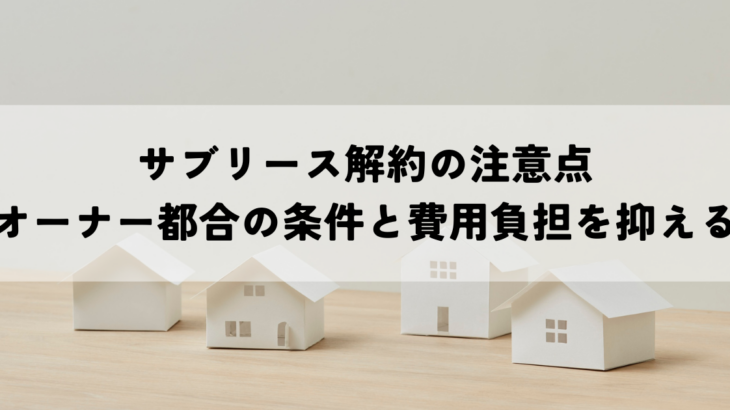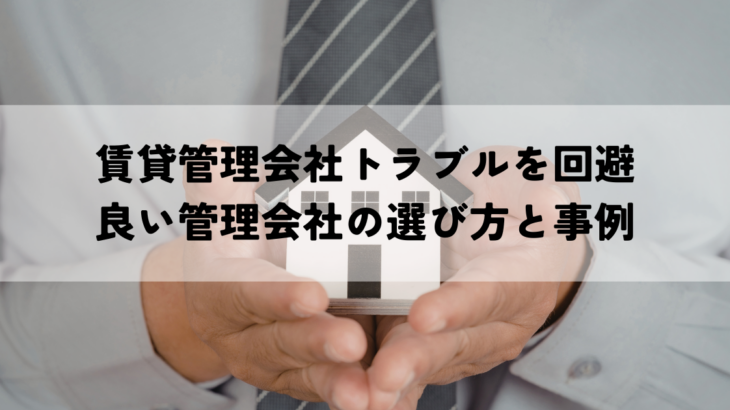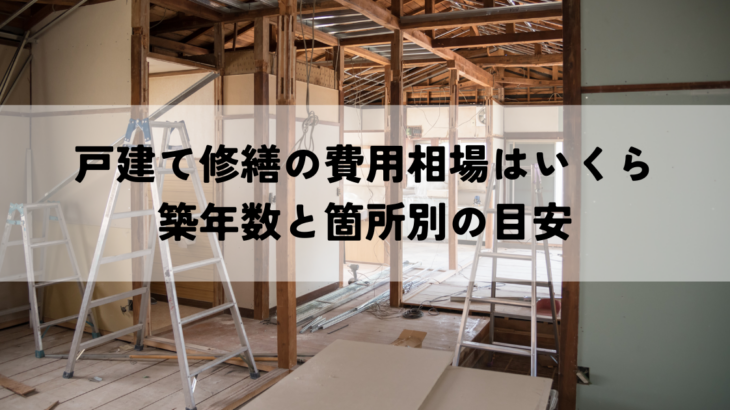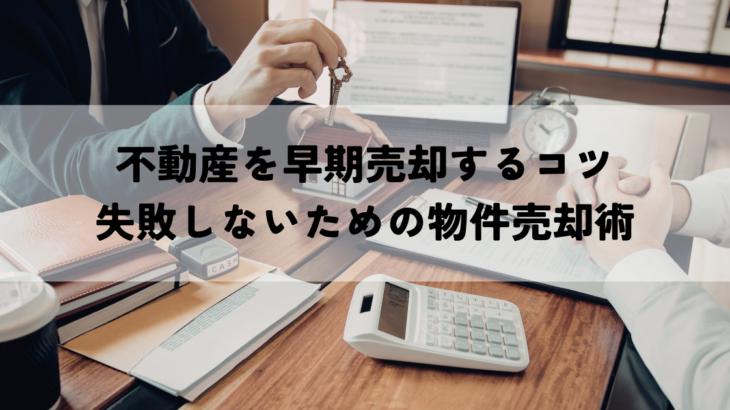不動産売却は人生における大きなイベントです。
売却益を得られる一方で、税金に関する不安を抱えている方も多いのではないでしょうか。
特に、譲渡所得税と基礎控除の関係は複雑で、理解しにくい点も多いでしょう。
そこで今回は、不動産売却における基礎控除の適用条件と計算方法について、具体的な事例を交えながら解説します。
税金対策の一助として、ぜひご活用ください。
不動産売却と基礎控除
基礎控除とは何か
基礎控除とは、所得税の計算において、総所得金額から差し引かれる一定の金額です。
令和2年度以降は、合計所得金額によって控除額が変動します。
2400万円以下であれば48万円、2400万円超2450万円以下であれば32万円、2450万円超2500万円以下であれば16万円が控除され、2500万円を超える場合は控除がありません。
令和元年度までは、合計所得金額に関わらず38万円の控除が適用されていました。
基礎控除の計算方法
基礎控除の計算は、まず合計所得金額を算出することから始まります。
合計所得金額とは、給与所得、事業所得、不動産譲渡所得など、全ての所得を合計した金額です。
この合計所得金額に基づき、上記の通り控除額が決定されます。
不動産売却による譲渡所得は、売却価格から取得費(購入価格、売却費用など)を差し引いた金額です。
この譲渡所得が合計所得金額に加算されます。
適用条件の確認
基礎控除の適用には、合計所得金額が2500万円以下であることが条件です。
ただし、重要なのは、この合計所得金額は特別控除前の金額である点です。
例えば、居住用財産の売却による3000万円特別控除を受ける場合、この特別控除前の金額で判定されます。
そのため、高額な不動産売却益がある場合、特別控除を適用しても、合計所得金額が2500万円を超え、基礎控除が適用されない可能性があります。

基礎控除の適用と注意点
譲渡所得の計算
譲渡所得の計算は、売却価格から取得費と売却費用を差し引くことで算出します。
取得費には、購入時の価格、修繕費用、不動産取得税などが含まれます。
売却費用には、仲介手数料、広告宣伝費などが含まれます。
所有期間が5年以内と5年以上では税率が異なるため、所有期間も確認する必要があります。
5年以内は短期譲渡所得、5年以上は長期譲渡所得となり、税率が異なります。
税金計算のポイント
税金計算では、譲渡所得から基礎控除を差し引いた金額が課税対象となります。
基礎控除が適用されない場合は、譲渡所得全額が課税対象となります。
さらに、居住用財産売却の場合は3000万円の特別控除が適用できる可能性があり、この特別控除は、譲渡所得から3000万円を差し引くことで税額を軽減できます。
ただし、適用条件がありますので、事前に確認が必要です。
よくある質問と回答
Q1:相続した不動産を売却する場合、基礎控除は適用されますか。
A1:相続した不動産の取得費が不明な場合が多く、譲渡所得の大部分が課税対象となる可能性が高いです。
そのため、合計所得金額が2500万円を超える可能性があり、基礎控除が適用されないケースも考えられます。
Q2:年末調整済みのサラリーマンが自宅を売却した場合、基礎控除はどうなりますか。
A2:給与所得と不動産譲渡所得を合計した金額(特別控除前)が2500万円を超える場合は、基礎控除が適用されない可能性があります。
確定申告が必要となります。

まとめ
不動産売却における基礎控除は、合計所得金額が2500万円以下であることが適用条件です。
ただし、特別控除前の金額で判定されるため、高額な不動産売却益がある場合は注意が必要です。
譲渡所得の計算は、売却価格から取得費と売却費用を差し引き、所有期間によって税率が異なります。
税金計算では、譲渡所得から基礎控除、そして居住用財産の場合は3000万円特別控除を差し引いた金額が課税対象となります。
相続した不動産や年末調整済みのサラリーマンが自宅を売却する場合も、合計所得金額が2500万円を超える可能性があり、基礎控除が適用されないケースがあります。
これらの点を踏まえ、税金対策を検討することが重要です。