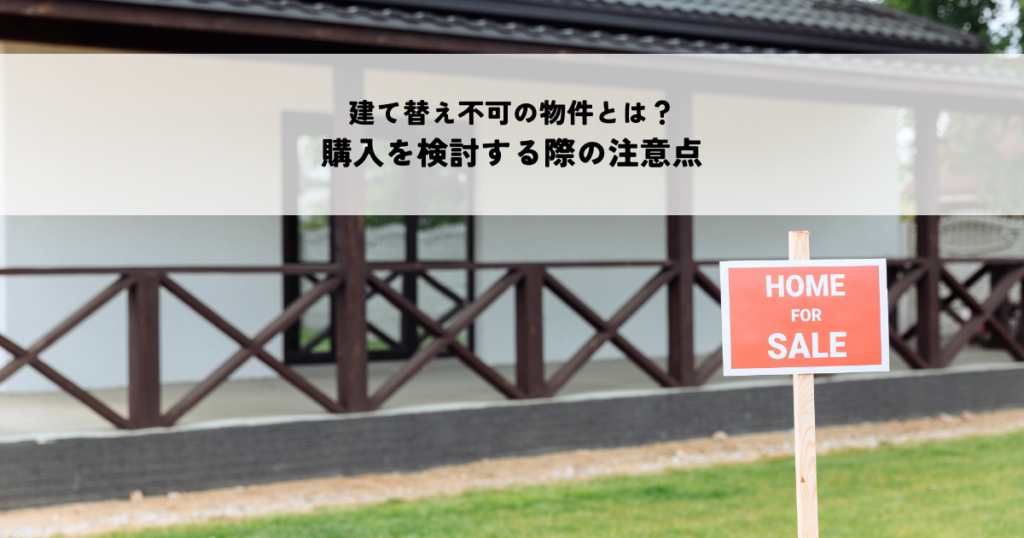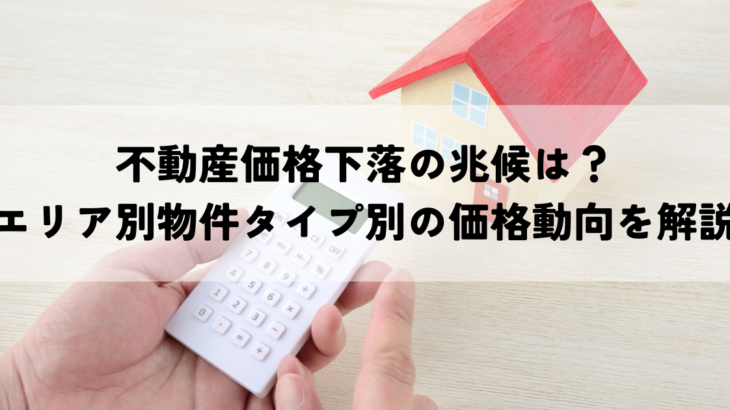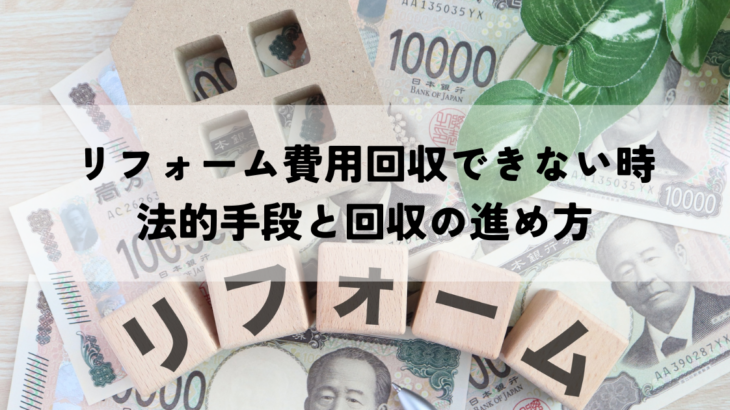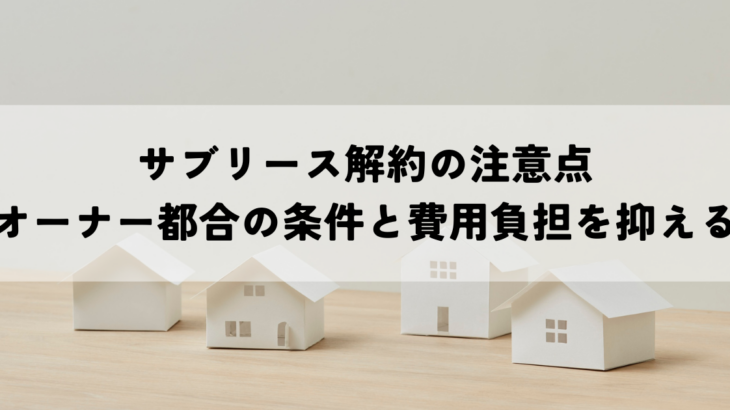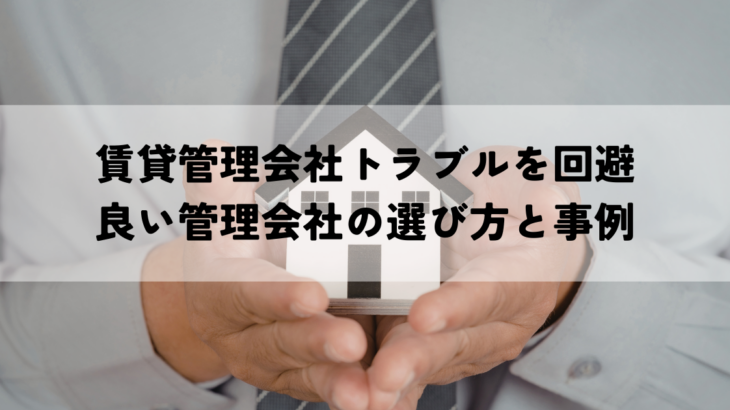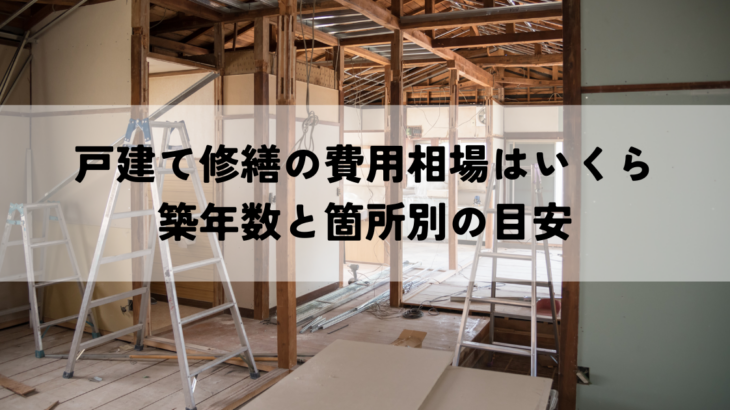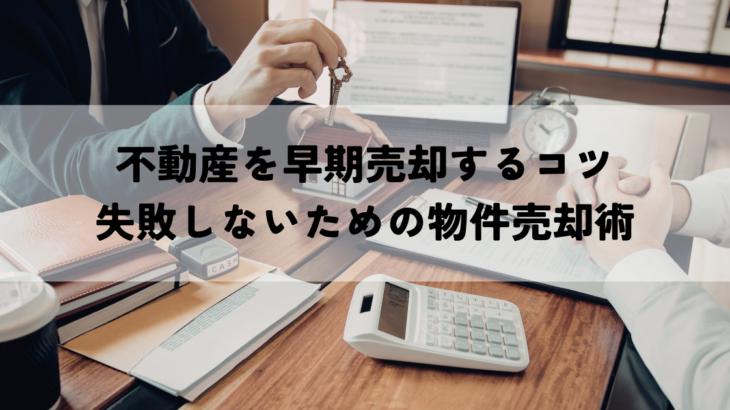老朽化した住宅に住み続け、将来の住まいについて不安を抱えている方も少なくないのではないでしょうか。
特に、現在の住宅を建て替えられない可能性がある場合、その不安はさらに大きくなるでしょう。
しかし、建て替えができない物件は、必ずしも選択肢がないわけではありません。
むしろ、適切な知識と対策によって、安心して暮らせる未来を築ける可能性を秘めているのです。
今回は、建て替えができない物件を購入する際の注意点について解説します。
再建築不可物件の定義と確認事項
再建築不可とは何か
再建築不可物件とは、既存の建物を解体し、更地にした場合に、新たな建物を建築することができない土地のことです。
これは、建築基準法で定められた「接道義務」を満たしていないことが主な原因です。
接道義務とは、一定の幅員を持つ道路に、一定の長さで接している必要があるという規定です。
具体的には、幅員4メートル以上の道路に2メートル以上接している必要があります。
この条件を満たしていない土地では、新たに建物を建てることができません。
接道義務と確認方法
接道義務の確認方法は、まず対象となる土地が接している道路の幅員と、接道部分の長さを確認することです。
測量図や登記簿を確認することで、正確な情報を得ることができます。
また、市町村の都市計画課に問い合わせることで、その土地が建築基準法上の道路に接しているかどうかも確認できます。
建ぺい率・容積率の確認
建ぺい率や容積率も、建築可能な建物の規模を制限する重要な要素です。
建ぺい率は敷地面積に対する建築面積の割合、容積率は敷地面積に対する建築延床面積の割合を示します。
これらの数値が低いと、建築可能な建物の規模が小さくなるため、注意が必要です。
これらの数値は、市町村の都市計画課で確認できます。
調査の重要性と専門家への依頼
再建築不可物件を購入する際には、専門家による調査が不可欠です。
建築士や不動産鑑定士などに依頼することで、接道状況や建物の構造、地盤状況などを正確に把握し、潜在的なリスクを事前に特定することができます。
専門家の意見を参考にすれば、購入後のトラブルを回避し、安心して物件を選ぶことができます。

再建築不可物件の購入とリスク管理
物件価格と将来的な価値
再建築不可物件は、建て替えができないため、一般的に市場価格よりも低い価格で取引されます。
しかし、価格の安さだけで判断するのではなく、将来的な価値についても考慮する必要があります。
例えば、リフォームによって居住性を向上させたり、土地の活用方法を検討したりすることで、資産価値を維持・向上させることも可能です。
融資における注意点
再建築不可物件は、担保価値が低いと見なされるため、住宅ローンの融資が受けにくい場合があります。
金融機関によっては、融資を断られる可能性もあるため、事前に複数の金融機関に相談し、融資条件を確認することが重要です。
自己資金を多く用意する、あるいは、他の融資方法を検討する必要があるかもしれません。
建て替えの現実的な検討
再建築不可物件であっても、接道状況などを改善することで、建て替えを可能にするケースもあります。
例えば、隣接地を購入したり、道路の位置指定を申請したりするといった方法が考えられます。
しかし、これらの方法は費用と時間がかかるため、現実的な可能性を慎重に検討する必要があります。
費用対効果をしっかり計算し、専門家と相談して判断しましょう。
リスク軽減のための対策
再建築不可物件を購入する際には、様々なリスクを想定し、適切な対策を講じる必要があります。
例えば、建物の老朽化対策としてリフォームを行う、自然災害対策として保険に加入するなどです。
売却価格が下がる可能性を常に念頭に置いて、購入を検討する必要があります。

まとめ
再建築不可物件は、価格が安いというメリットがある一方で、建て替えができないという大きなデメリットがあります。
購入を検討する際には、接道状況や建物の状態、将来的な価値などを慎重に検討する必要があります。
専門家による調査やアドバイスを受けることで、リスクを軽減し、安心して物件を選ぶことができるでしょう。
融資の可否や、リフォーム、売却時のリスクについても事前に十分な調査を行いましょう。
後悔しない選択をするために、時間をかけて、じっくりと検討することが大切です。