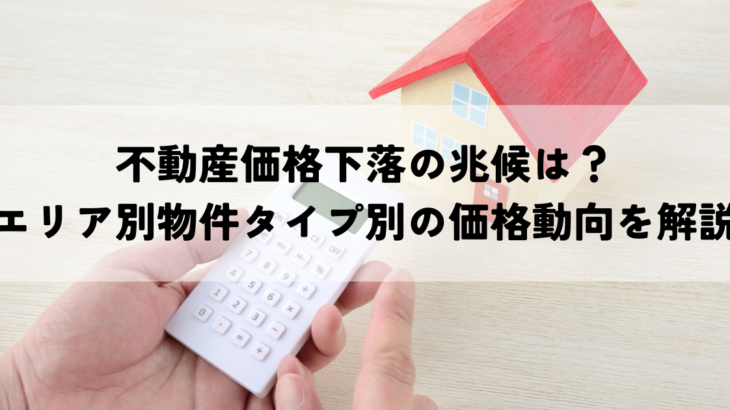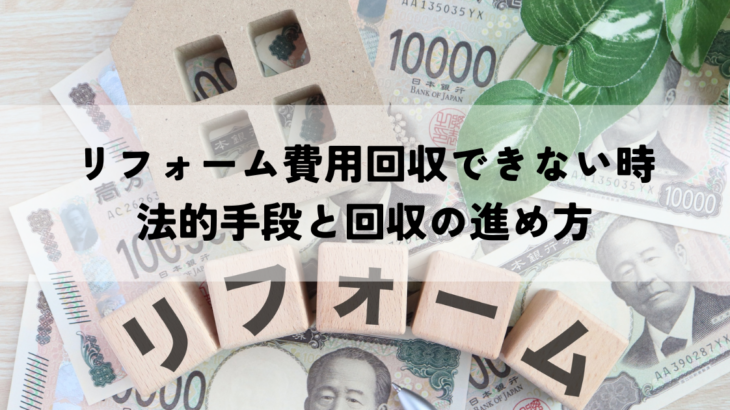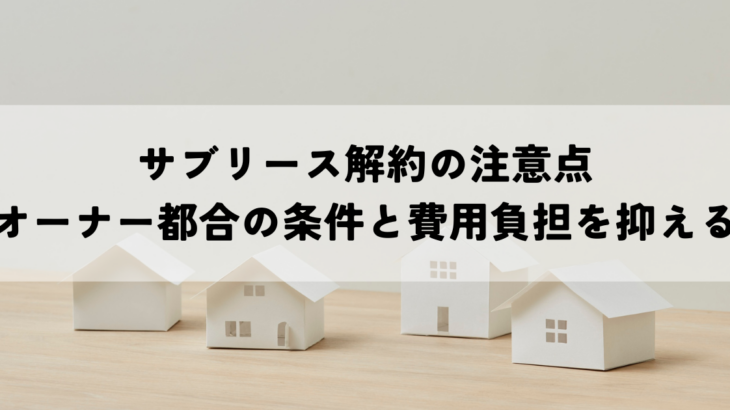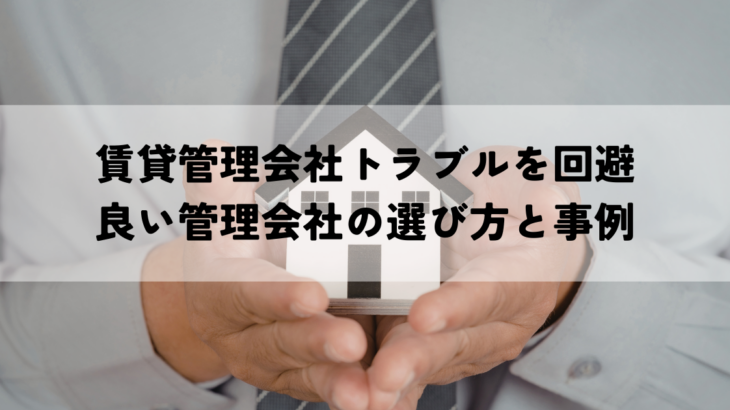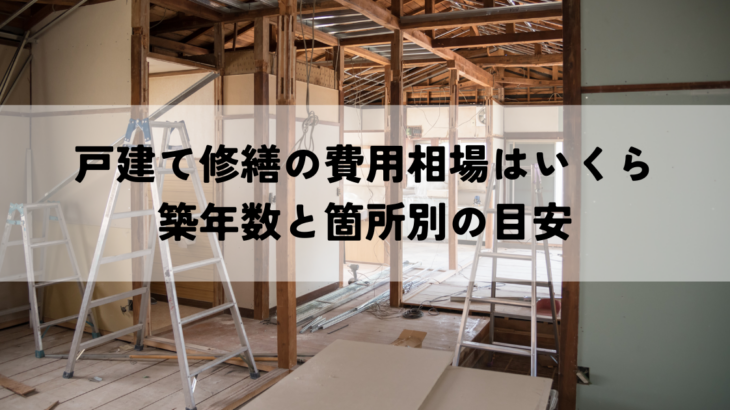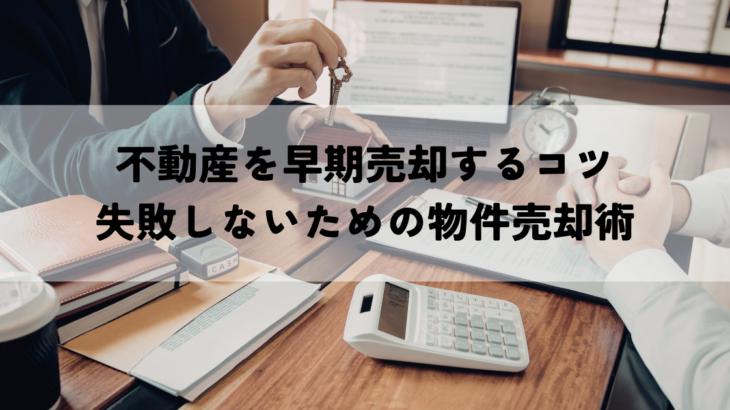共有名義の不動産を持っている、あるいはこれから取得しようと考えている方にとって、固定資産税の扱いは重要な関心事でしょう。
共有者が複数いる場合、誰がどのように固定資産税を負担するのか、滞納した場合のリスクは何か、といった疑問を持つのは当然です。
今回は、共有名義の不動産における固定資産税の仕組み、滞納時のリスクと対処法について解説します。
共有名義の不動産の固定資産税の仕組み
固定資産税の計算方法と共有持分の関係
固定資産税は、毎年1月1日時点の不動産所有者に対して課税されます。
共有名義の場合、各共有者の持分割合に応じて固定資産税が按分されます。
例えば、不動産の評価額が1,000万円で、AさんとBさんが2分の1ずつ共有している場合、AさんとBさんはそれぞれ500万円分の評価額に対して固定資産税を負担することになります。
また、共有者間で異なる持分割合が設定されている場合も、その割合に応じて按分されます。
例えば、Aさんが3分の2、Bさんが3分の1の持分を持っている場合、Aさんは666万6667円分、Bさんは333万3333円分の評価額に対して固定資産税を負担することになります。
さらに、この計算は、各自治体が算出した評価額と固定資産税率に基づいて行われるのです。
納税通知書の送付先
原則として、納税通知書は各共有者に対して送付されます。
しかし、各自治体によっては、代表者1名にまとめて送付される場合もあります。
その場合でも、各共有者は自分の持分割合に応じた納税義務を負います。
誰が納税通知書を受け取るかではなく、誰が所有者として登録されているかが重要なのです。
また、代表者宛に送付される場合、代表者は他の共有者に納税義務があることを伝え、適切な納税が行われるように協力する必要があります。
さらに、代表者への送付はあくまで事務手続きの簡略化であり、個々の納税義務を免除するものではないことを理解しておくべきでしょう。
共有者間の負担割合はどうやって決める?
固定資産税の負担割合は、原則として共有持分の割合に応じて決定されます。
しかし、共有者間で別途合意があれば、その合意に基づいて負担割合を変更することも可能です。
例えば、共有持分が2分の1ずつであっても、一方の共有者が固定資産税の全額を負担することで合意することもできます。
このような合意は書面に残しておくことが望ましいといえます。
なぜなら、口約束だけでは、後々トラブルに発展する可能性があるからです。
また、合意内容に変更が生じた場合も、速やかに書面を更新することで、誤解や紛争を防ぐことができます。
固定資産税の共有名義を変更できる?
共有持分の変更や共有者の追加・削除など、共有名義の変更は可能です。
ただし、これには所有権の移転を伴うため、不動産の登記手続きが必要になります。
また、変更に伴い、新たな共有者間で固定資産税の負担割合について合意を形成する必要があります。
この合意も書面に残しておくことが推奨されます。
加えて、変更後の持分に応じた固定資産税の負担割合を明確にし、関係者全員が理解していることを確認することが大切です。
これらの手続きを適切に行うことで、将来的なトラブルを回避できるでしょう。

固定資産税を滞納したらどうなる?共有名義の場合のリスクと対処法
共有者が固定資産税を滞納した場合
共有名義の不動産で1人でも共有者が固定資産税を滞納した場合、自治体は共有者全員に対して督促状を送付します。
滞納が続くと、延滞金が発生するだけでなく、最終的には不動産が差し押さえられる可能性があります。
これは、共有者全員が連帯して納税義務を負うためです。
つまり、自分がきちんと納税していても、他の共有者が滞納すれば、自分の財産にも影響が及ぶ可能性があります。
そのため、共有者間で定期的に連絡を取り合い、納税状況を確認し合うことが重要になります。
固定資産税の滞納で財産が差し押さえられるケース
固定資産税の滞納が長期間にわたると、自治体は不動産を差し押さえることができます。
差し押さえられた不動産は、競売にかけられ、売却代金から滞納分の固定資産税や延滞金が回収されます。
競売によって不動産を失う可能性があるため、滞納には十分注意する必要があります。
また、競売手続きには時間と費用がかかるため、所有者にとって大きな負担となるでしょう。
さらに、売却額が滞納額に満たない場合、残額の支払いを求められる可能性もあります。
共有持分だけ差し押さえられることはある?
共有持分のみの差し押さえも可能です。
例えば、AさんとBさんが共有している不動産において、Aさんが固定資産税を滞納した場合、Aさんの持分だけが差し押さえられる可能性があります。
この場合、Bさんの持分は直接影響を受けません。
しかし、Aさんの持分が競売にかけられると、新たな共有者が現れる可能性があり、Bさんにとっては望ましくない状況になるかもしれません。
そのため、BさんはAさんの滞納を放置せず、何らかの対策を講じる必要があるといえます。
例えば、Aさんに納税を促したり、Aさんの持分を買い取ったりするなどの方法が考えられます。
滞納を防ぐための共有者間での対策
共有者間で固定資産税の納付状況を定期的に確認し合うことが重要です。
また、納税の責任者を明確にする、あるいは共同の口座から自動引き落としで納付するなどの対策も有効です。
さらに、共有者間で固定資産税に関する合意書を作成し、負担割合や納付方法などを明確にしておくことで、将来的なトラブルを予防することができます。
また、各自治体の相談窓口を利用するなど、外部の専門機関に相談することも有効な手段です。
専門家のアドバイスを受けることで、より適切な対策を立てることができるでしょう。

まとめ
共有名義の不動産における固定資産税は、共有者全員が連帯責任を負うため、滞納のリスクを理解し、適切な対策を講じることが重要です。
共有者間でしっかりとコミュニケーションを取り、納税に関するルールを明確化することで、トラブルを未然に防ぎ、安心して不動産を共有することができます。
そのためにも、本記事で解説した内容を参考に、共有者間で十分に話し合い、合意形成を図ることが大切です。
また、必要に応じて専門家の助言を求めることも検討しましょう。