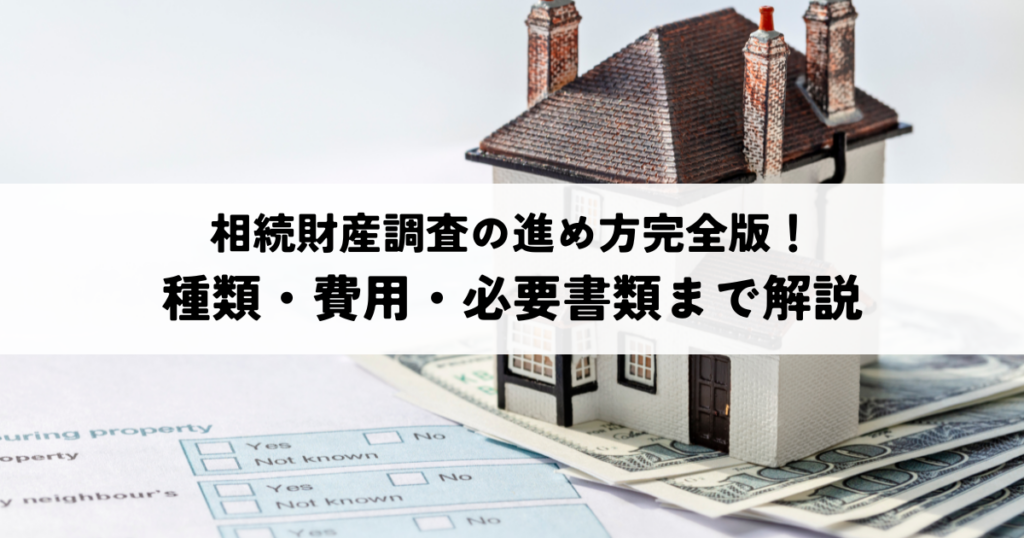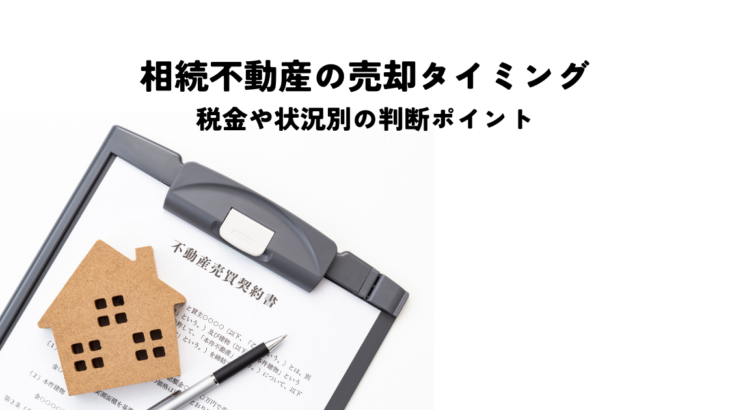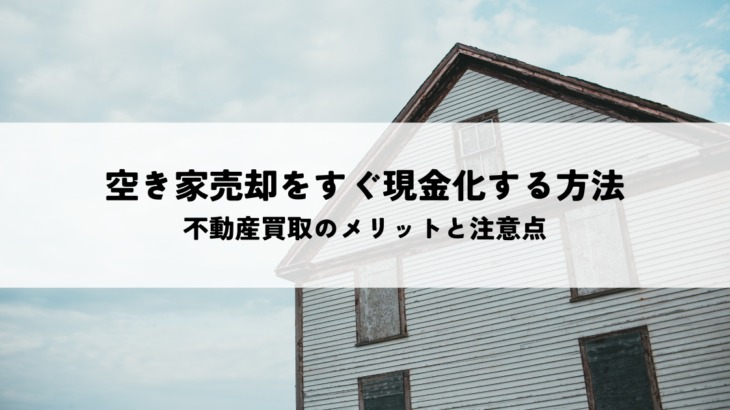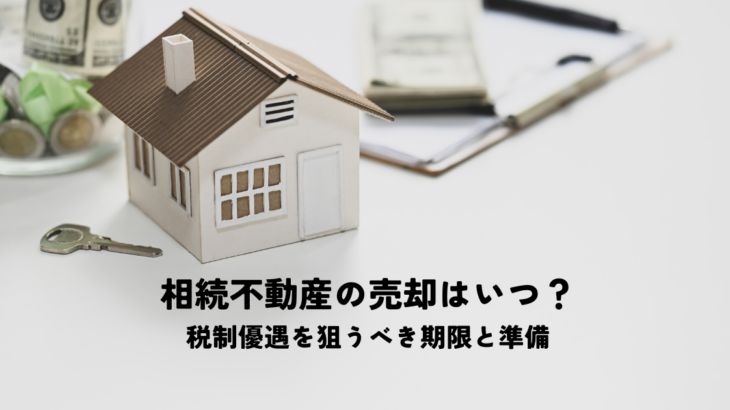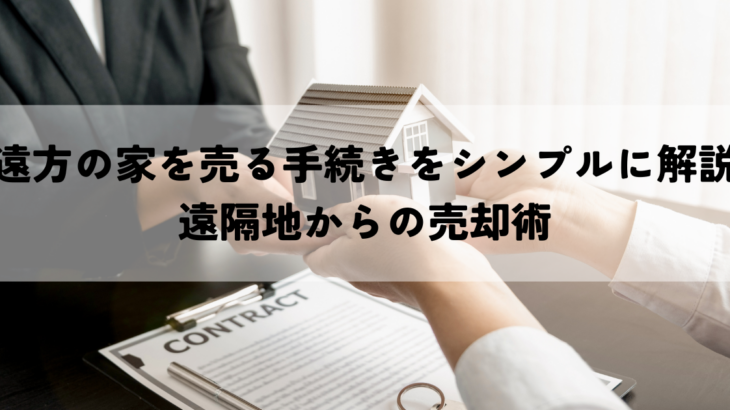相続手続きを進める上で、まず重要なのが相続財産の調査です。
遺された財産を正確に把握することは、相続手続きを円滑に進めるために不可欠であり、相続人同士のトラブルを防ぐためにも非常に重要といえます。
今回は、相続財産調査の方法について、具体的な手順や必要な書類、費用の目安などを解説します。
相続財産調査の方法
相続財産調査の全体像を把握する
相続財産調査は、故人の残した財産を漏れなく特定するための作業です。
銀行預金や証券口座などの金融資産、不動産、自動車、生命保険金など、多岐にわたる財産を網羅的に調査する必要があります。
調査を進める上では、まず全体像を把握し、どのような財産が存在する可能性があるかをリストアップすることが重要です。
これは、後々の調査効率を大きく左右するのです。
また、相続人全員で協力し、故人の生活状況や所有物に関する情報を共有することで、より正確な調査が可能になります。
さらに、故人の趣味や交友関係なども手がかりになることがあります。
財産調査のステップを理解する
相続財産調査は、大きく分けて情報収集、調査、確認の3つのステップに分かれます。
まず、故人の遺言書や通帳、証券などの書類を収集し、財産の目録を作成します。
次に、銀行や証券会社、不動産会社など、該当する機関に問い合わせを行い、具体的な財産内容を確認します。
最後に、収集した情報を元に、相続財産の総額を算出し、相続人への分配方法を決定します。
各ステップにおいて、必要な書類や手続きを事前に確認しておくことで、スムーズな調査を進めることができます。
例えば、金融機関への問い合わせには、故人の口座情報や取引履歴が必要となる場合もあります。
相続財産の種類をリストアップする
相続財産には、預貯金、株式・投資信託などの金融資産、不動産、自動車、生命保険金が含まれます。
また、著作権などの知的財産権、現金や貴金属などの動産も含まれます。
これらは、調査方法や必要な書類がそれぞれ異なるため、個別にリストアップし、それぞれについて調査を進めることが重要です。
例えば、不動産の調査には、登記簿謄本や固定資産税評価証明書が必要となります。
さらに、故人が事業を営んでいた場合は、事業に関する資産についても調査する必要があります。
負債も相続財産に含まれるため、借金や未払金なども調査対象となります。
財産調査に必要な書類を確認する
相続財産調査を進めるためには、故人の戸籍謄本、住民票、遺言書、遺産分割協議書などの書類が必要となります。
そのため、これらの書類は早めに準備しておくことが重要です。
また、これ以外にも、銀行や証券会社、不動産会社などから取得する書類が必要になります。
例えば、銀行口座の調査には預金通帳の写し、証券口座の調査には証券口座開設時の書類などが必要になります。
これらの書類は、調査の効率化と正確性の向上に大きく貢献します。
さらに、事前に必要な書類をリスト化し、準備しておくことで、スムーズな調査進行が可能になります。

金融機関の財産調査方法は?
銀行口座の調査方法を理解する
故人の銀行口座を調査するには、相続人の戸籍謄本と相続関係説明図、そして故人の預金通帳またはキャッシュカードが必要となる場合が多いです。
金融機関の窓口にこれらの書類を提示し、相続手続きを進めることで、口座残高を確認できます。
ただし、金融機関によっては、相続手続きに必要な書類が異なる場合もありますので、事前に確認が必要です。
加えて、インターネットバンキングを利用していた場合は、取引履歴なども確認する必要があります。
証券口座の調査方法を知る
証券口座の調査は、銀行口座と同様に相続人の身分証明書と相続関係を証明する書類が必要となります。
証券会社に連絡を取り、相続手続きの方法を尋ね、必要な書類を提出することで、証券口座の残高や保有銘柄を確認することができます。
証券会社によってはオンラインでの手続きに対応している場合もあるため、事前に確認することをお勧めします。
また、株式だけでなく、投資信託や債券なども含まれる場合があるので、注意が必要です。
保険金の有無を調べる方法
生命保険金の有無を調べるには、故人が加入していた保険会社を特定する必要があります。
故人の書類や遺品などを調べ、保険証券を探したり、保険会社に問い合わせることで、保険金の有無や受取人を確認できます。
保険金の受取人は契約時に指定されているため、その旨を事前に確認しておくことが大切です。
また、生命保険だけでなく、損害保険についても確認する必要があります。
さらに、保険金以外にも、死亡退職金や弔慰金なども確認しておきましょう。

不動産の財産調査方法は?
不動産登記簿謄本を取得する
不動産の調査には、まず不動産登記簿謄本を取得する必要があります。
これは、法務局で申請することで取得できます。
登記簿謄本には、不動産の所在地、所有者、面積などの情報が記載されており、故人が所有する不動産を特定する上で重要な資料となります。
また、登記簿謄本はオンラインでも取得可能です。
さらに、不動産が共有持分の場合は、その持分比率も確認する必要があります。
固定資産税評価証明書を確認する
不動産の評価額を知るためには、固定資産税評価証明書を確認する必要があります。
これは、市町村役場で申請することで取得できます。
評価額は、相続税の計算などに必要となるため、取得しておくことが大切です。
また、固定資産税評価証明書もオンラインで取得できる場合があります。
さらに、評価額は毎年変動するため、最新のものを取得する必要があります。
不動産名義変更の手続きを理解する
不動産の名義変更は、相続手続きの中でも複雑な手続きの一つです。
相続登記の手続きを進めるためには、相続関係を証明する書類や不動産登記簿謄本などの書類が必要となります。
司法書士などの専門家に依頼することで、スムーズな手続きを進めることができます。
また、名義変更には登録免許税などの費用も発生します。
さらに、不動産が共有財産の場合は、遺産分割協議が必要となります。
相続財産調査の費用と時間は?
財産調査にかかる費用の目安を知る
相続財産調査にかかる費用は、調査の規模や難易度によって大きく異なります。
金融機関や不動産会社への問い合わせ費用、専門家への相談費用などが発生する可能性があります。
費用を抑えるためには、可能な範囲で自分で調査を進めることも有効ですが、複雑な手続きや専門的な知識が必要な場合は、専門家に依頼することを検討しましょう。
例えば、司法書士に相続登記を依頼する場合、費用は不動産の評価額によって異なります。
財産調査に必要な期間を把握する
財産調査に必要な期間は、財産の規模や種類、調査の進捗状況などによって異なります。
簡単な調査であれば数週間で完了することもありますが、複雑な調査の場合は数ヶ月かかることもあります。
余裕を持って調査を進めるためにも、早めの準備が重要です。
また、相続人が複数いる場合は、遺産分割協議に時間がかかる場合もあります。
財産調査で困った時の対処法
専門家への相談窓口を知る
相続財産調査で困った際は、弁護士や税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
弁護士は法律的な問題に関するアドバイスを行い、税理士は税金に関する専門的な知識を提供してくれます。
それぞれの専門家の得意分野を理解し、適切な専門家に相談することで、より効率的な解決策を見つけることができるでしょう。
例えば、相続人間で遺産分割協議がまとまらない場合は、弁護士に相談することで解決の糸口が見つかるかもしれません。
相続専門の弁護士に依頼するメリット
相続専門の弁護士は、相続に関する豊富な知識と経験を有しており、複雑な相続問題に対処することができます。
弁護士に依頼することで、相続手続きをスムーズに進めることができ、相続人同士のトラブルを未然に防ぐことも期待できます。
また、弁護士は遺産分割協議の代理人として交渉を行うこともできます。
さらに、遺言書の作成や相続放棄の手続きについてもサポートを受けることができます。
税理士に相談するメリット
税理士は、相続税の計算や申告に関する専門的な知識を有しています。
相続税の申告は複雑な手続きであるため、税理士に依頼することで、正確な申告を行い、税負担を軽減することが期待できます。
また、税理士は相続税の申告だけでなく、生前贈与や事業承継など、相続に関する税務全般について相談することができます。
さらに、税務調査への対応もサポートしてくれます。
まとめ
今回は、相続財産調査の方法について、具体的な手順や必要な書類、費用の目安などを解説しました。