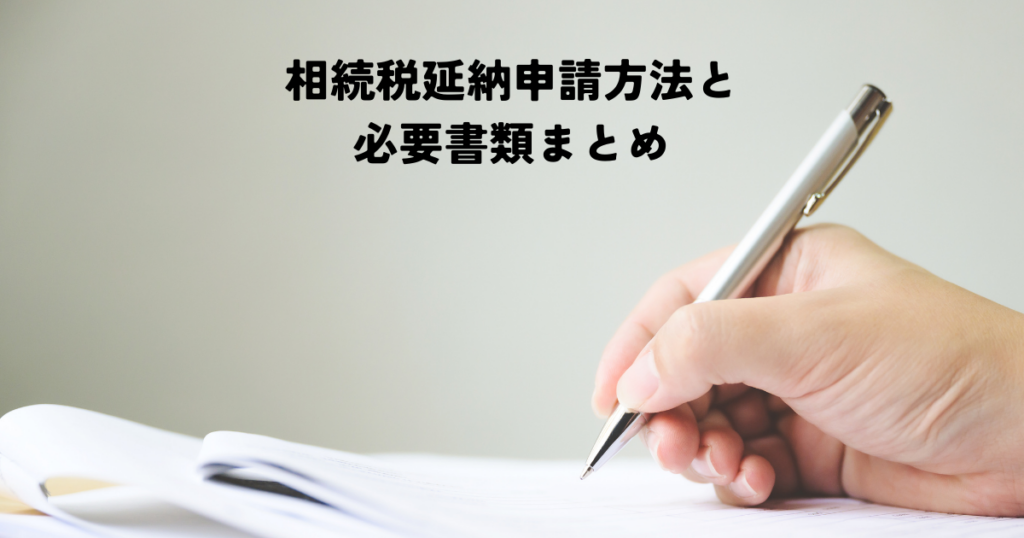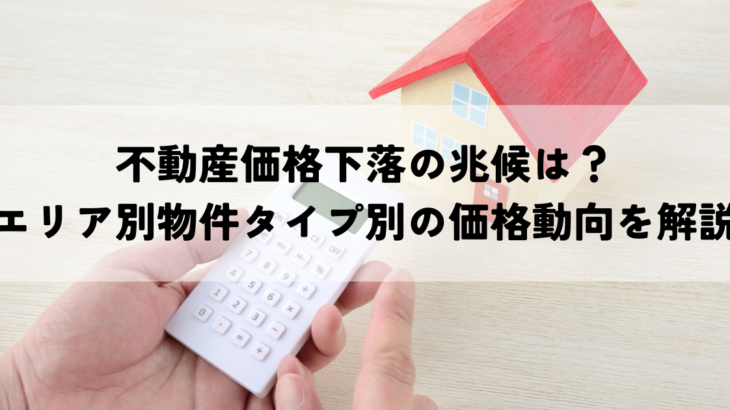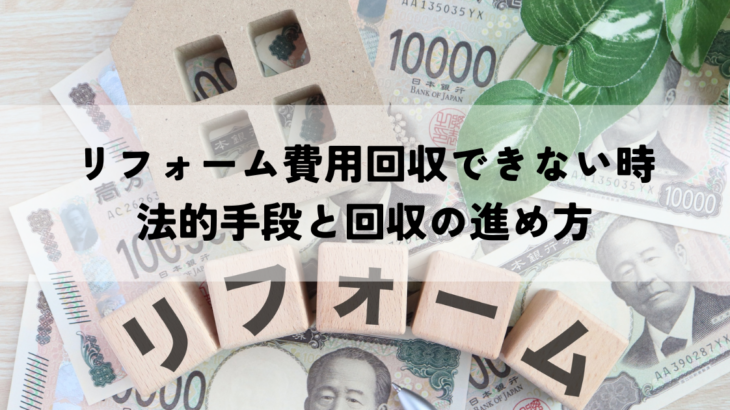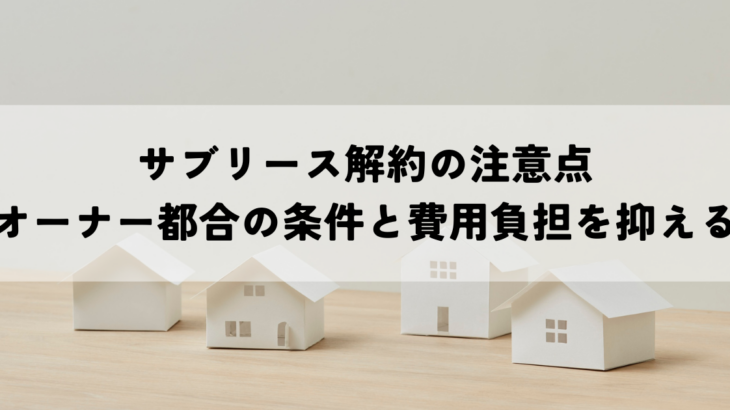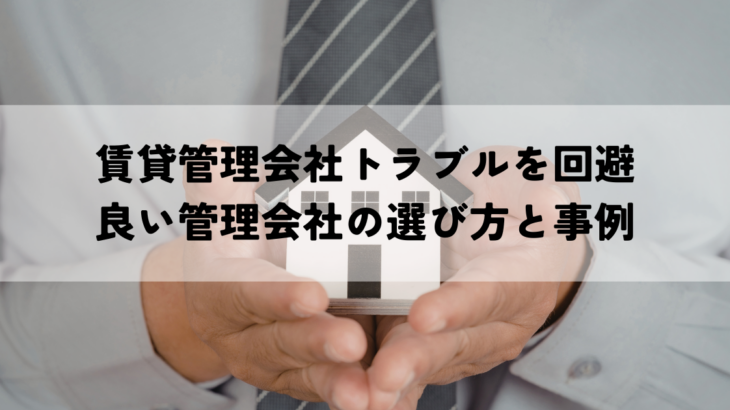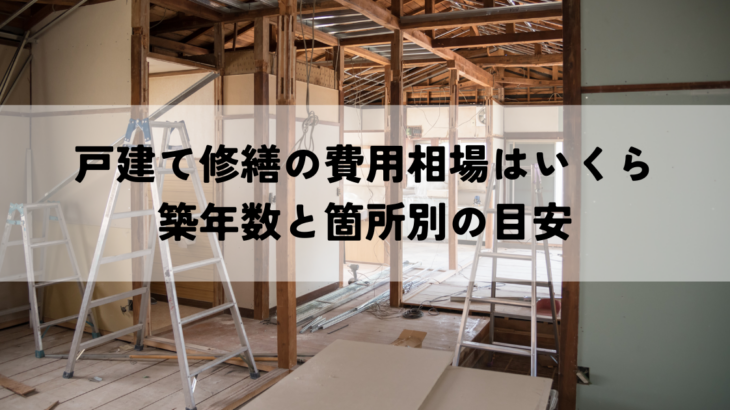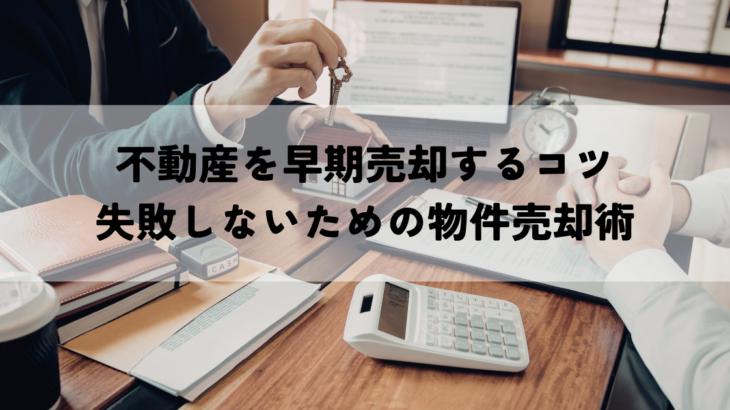相続税の納付に不安を抱えている方にとって、延納制度は大きな救世主となる可能性があります。
しかし、その申請手続きは複雑で、何を準備すれば良いのか、どこに申し出れば良いのか分からず、戸惑う方も少なくないでしょう。
今回は、相続税の延納申請について、申請できるケース、必要な書類、申請方法、そして具体的な手順まで、分かりやすく解説します。
相続税の延納申請はどんな時にできる?
相続税の納付が困難な場合に延納が認められる
相続税の納付期限が迫っているにも関わらず、現金や預金が不足している場合、相続税の納付が困難であると認められれば延納が認められる可能性があります。
具体的には、相続財産の評価額に対して、預金や現金などの手持ち資金が著しく不足しており、売却可能な資産も限られているなど、客観的に納税が困難であると判断される状況が必要です。
また、相続財産を売却してもすぐに納税資金を確保できない場合も、延納が検討される要素となります。
さらに、これらの状況を証明する客観的な資料の提出も求められる場合があるのです。
延納できる金額に上限がある
延納が認められたとしても、延納できる金額には上限があります。
これは、税務署が納税者の財産状況を精査し、無理なく返済できる範囲内で設定されます。
そのため、相続税全額の延納が認められるとは限りません。
また、担保の提供を求められる場合もあるため、事前に確認しておくことが重要といえます。
さらに、延納期間中に発生する利息についても理解しておく必要があるでしょう。
延納期間は最長で20年
延納が認められた場合、最長で20年という長い期間に渡って分割納付が可能となります。
しかし、延納期間は個々の状況に応じて決定され、必ずしも20年が認められるとは限りません。
例えば、相続財産の状況や納税者の返済能力などが考慮されます。
また、延納期間が長くなるほど、利息負担も大きくなるため、注意が必要です。

延納申請に必要な書類
相続税申告書
相続税の申告は、相続発生から10ヶ月以内に行う必要があります。
延納申請を行う際には、この相続税申告書が必須です。
申告書には、相続財産の状況、相続人の状況、相続税の計算などが詳細に記載されています。
そのため、正確な情報を漏れなく記載することが重要となります。
延納申請書
税務署が定めた様式に則って、延納を申請する旨を記した書類です。
申請者の氏名、住所、相続税の納付金額、延納を希望する期間、担保の有無などを正確に記入する必要があります。
また、延納の理由や納付計画についても具体的に記載することで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。
さらに、必要に応じて添付書類が必要となる場合もあるため、事前に確認することが重要です。
財産目録
相続財産の全てを詳細に記載した書類です。
不動産、預貯金、株式、その他の動産など、全ての財産とその評価額を正確に記載する必要があります。
これは、税務署が納税者の財産状況を把握し、延納の可否、延納金額の上限を判断するために不可欠です。
また、財産目録の作成には専門的な知識が必要となる場合もあるため、税理士などの専門家に相談することも有効な手段といえます。
納税猶予担保提供書(担保を提供する場合)
延納が認められるかどうかは、税務署の判断によりますが、多くの場合、担保の提供が求められます。
担保としては、不動産や預貯金などが考えられます。
担保を提供する場合は、この書類に担保の内容を明確に記載する必要があります。
担保の評価額が延納金額を上回る必要がある場合もあるため、注意が必要です。

相続税の延納申請方法は?
申請書類を税務署に提出する
延納申請に必要な書類を全て揃え、管轄の税務署に提出します。
提出方法は、郵送や窓口での持参が可能です。
窓口で提出する場合、事前に予約が必要な場合もあるため、確認することをお勧めします。
申請は相続税の申告期限までに行う
延納申請は、相続税の申告期限(相続発生から10ヶ月後)までに済ませておく必要があります。
期限を過ぎて申請した場合、延納が認められない可能性が高いため、注意が必要です。
そのため、余裕を持って準備を進めることが重要です。
オンライン申請はできない
現在のところ、相続税の延納申請はオンラインでは行えません。
必ず、書面で申請する必要があります。
ただし、将来的にはオンライン申請が可能になる可能性もあるため、最新の情報を確認しておくことが大切です。
延納申請の具体的な手順は?
必要書類を集める
まず、相続税申告書、延納申請書、財産目録など、延納申請に必要な書類を全て揃えます。
特に財産目録は、相続した全ての財産を漏れなく記載する必要があるため、時間と手間がかかります。
そのため、早めに準備を始め、必要に応じて専門家に相談することも検討しましょう。
延納申請書を作成する
税務署から入手した様式に沿って、延納申請書を作成します。
必要事項を正確に記入し、誤字脱字がないように注意深く確認しましょう。
不明な点があれば、税務署に問い合わせることも可能です。
また、延納の理由や納付計画を具体的に記載することで、申請がスムーズに進む可能性が高まります。
相続税申告書と一緒に税務署へ提出する
作成した延納申請書と、相続税申告書、財産目録などをまとめて、管轄の税務署へ提出します。
提出方法は、郵送か窓口持参のどちらかを選択できます。
窓口で提出する場合は、事前に税務署に連絡し、必要書類や手続きを確認しておきましょう。
税務署からの連絡を待つ
税務署は、提出された書類を審査し、延納の可否を決定します。
審査には一定の期間を要するため、税務署からの連絡を待ちましょう。
審査結果によっては、追加の書類提出や面談が必要になる場合もあります。
延納が認められる条件
客観的に納税が困難であること
延納を認められるためには、客観的に見て相続税の納付が困難であることを証明する必要があります。
具体的な証拠として、財産状況を示す資料や、売却困難な財産の状況などを提示する必要がある場合があります。
また、負債の状況なども考慮されるため、詳細な情報を提供することが重要です。
担保を提供できること(場合による)
延納が認められるかどうかは、税務署の判断によりますが、多くのケースで担保の提供が求められます。
担保を提供できることで、延納が認められる可能性が高まります。
担保として認められる財産の種類や評価額には一定の基準があるため、事前に確認しておくことが重要といえます。
分割納付では対応できないこと
分割納付制度では対応できないほど、納税が著しく困難な場合に、延納が検討されます。
分割納付制度と延納制度はそれぞれ異なる制度であり、状況に応じて適切な制度を選択する必要があります。
それぞれの制度の特徴や適用条件を理解し、自身に合った制度を選択することが大切です。
まとめ
相続税の延納申請は、相続税の納付が困難な場合に認められる制度です。
申請には、相続税申告書、延納申請書、財産目録などが必要で、相続税の申告期限までに税務署に提出する必要があります。
延納申請が認められるかどうかは、税務署の審査によるため、必要書類を正確に準備し、早めの申請が重要です。
不明な点があれば、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
また、延納が認められた場合でも、延納期間中の利息負担や担保の設定など、注意すべき点があるため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。